×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
外書の時間に聞いた面白いお話です。
昔々の中世イギリスでは、新石器時代の遺跡の数々は悪魔崇拝の象徴のように思われていたらしいです。
エーヴベリー(Avebury)もそういった巨石遺跡の一つなのですが(ストーンヘンジと同じ世界遺産です/先生曰く、「焼き鳥でいうとストーンヘンジがタレでエーヴベリーが塩」/どうして焼き鳥なんでしょうかねえ)、十四世紀、ある一人の怪しいおっさんゲフフン!悪魔祓いさんがこの地方を訪れたのだそうです。
この頃の悪魔祓いという職業は、床屋と医者と悪魔祓いを兼業しているようなものだったとか。
確かにヨーロッパの方の床屋は簡単な手術を行いますし、中世の宗教概念からいくと医者も悪魔祓いもごっちゃみたいなものですしねえ。
そんなわけでこのおっさんは早速エーヴベリーにそびえ立つ多くの巨石に目をつけます。
「これは悪魔の仕業に違いない! すぐに人々の目に留まらないようにしなければ!」
そうはいっても身の丈をはるかに超える馬鹿でかいシロモノです。
身一つで砕けるわけも無く、持ち運べる筈も無かったので、おっさんは地道に石を下から掘り出し、倒してしまうことにしました。
しかし……なんということでしょう!
おっさんは必死で穴を掘るあまり、石の倒れてくる方向を考えることを忘れていたようです。
あとはお察しの通りです。。
二十世紀にエーヴベリーの倒れた石を復元した郷土史学者さんが、石の下から彼の骨と遺品を発見したのだとか。
ハサミ(床屋さんですからね)、ランセット(お医者さんですからね)、コイン三枚(これによっておっさんの生きた時代が分かります/それにしても貧乏だったのでしょうか)などの遺品は、今現在、エーヴベリーの資料館に展示してあるらしいです。
ていうか、二十世紀になるまで誰も助けてやらなかったんですね……
昔々の中世イギリスでは、新石器時代の遺跡の数々は悪魔崇拝の象徴のように思われていたらしいです。
エーヴベリー(Avebury)もそういった巨石遺跡の一つなのですが(ストーンヘンジと同じ世界遺産です/先生曰く、「焼き鳥でいうとストーンヘンジがタレでエーヴベリーが塩」/どうして焼き鳥なんでしょうかねえ)、十四世紀、ある一人の怪しいおっさんゲフフン!悪魔祓いさんがこの地方を訪れたのだそうです。
この頃の悪魔祓いという職業は、床屋と医者と悪魔祓いを兼業しているようなものだったとか。
確かにヨーロッパの方の床屋は簡単な手術を行いますし、中世の宗教概念からいくと医者も悪魔祓いもごっちゃみたいなものですしねえ。
そんなわけでこのおっさんは早速エーヴベリーにそびえ立つ多くの巨石に目をつけます。
「これは悪魔の仕業に違いない! すぐに人々の目に留まらないようにしなければ!」
そうはいっても身の丈をはるかに超える馬鹿でかいシロモノです。
身一つで砕けるわけも無く、持ち運べる筈も無かったので、おっさんは地道に石を下から掘り出し、倒してしまうことにしました。
しかし……なんということでしょう!
おっさんは必死で穴を掘るあまり、石の倒れてくる方向を考えることを忘れていたようです。
あとはお察しの通りです。。
二十世紀にエーヴベリーの倒れた石を復元した郷土史学者さんが、石の下から彼の骨と遺品を発見したのだとか。
ハサミ(床屋さんですからね)、ランセット(お医者さんですからね)、コイン三枚(これによっておっさんの生きた時代が分かります/それにしても貧乏だったのでしょうか)などの遺品は、今現在、エーヴベリーの資料館に展示してあるらしいです。
ていうか、二十世紀になるまで誰も助けてやらなかったんですね……
PR
奈良でキトラ古墳の白虎さんに会ってきました!
というか、展示の仕方がスゴイですね……!
雨の降る中、外にはみ出している九十分待ちの長蛇の列。
▽
資料を眺めながら、資料館の中を延々と続く列に並ぶ。
▽
足が痛くなってきた頃に特別なお部屋にようやく到着。
▽
一列に並んで、二、三人ずつ順番に白虎と対面。
▽
十数秒後に係員のお姉さんがさっくりと次を促す。
えええ、そんな、一目千両ー!?
友達と一緒に行ったのですが、細かい議論の余地もありませんでした。。
しかしまあ、あれだけの数のお客さんをさばくにはしょうがないかもしれません。
ダ・ヴィンチ・コードミステリーSPとかいうものを見ています。
……こういうあからさまな便乗番組って嫌いなんですけどねえ……(何で見るんだ)
マリア説は京佐としても好きですし、ダ・ヴィンチ・コードも結構楽しんで読んだのですが、こういう風に「これが真実だ」みたいにやられるのって微妙です。
キリスト教徒の人たちにしてみれば不愉快甚だしいんでしょうしねえ。
世界ふしぎ発見とか、奇跡体験アンビリーバボーとか、あの辺の番組にも見え隠れする押し付けがましさみたいなものがある気がします。
嫌だ嫌だ。
ところで個人的にはモナ・リザをモチーフにした作品なら、カニグズバーグの「ジョコンダ夫人の肖像」の方が印象が深いです。
ダ・ヴィンチ・コードのダ・ヴィンチはどこまでも天才で仕掛け人で多くの謎を遺した人なのですが、ジョコンダ夫人の肖像のダ・ヴィンチはやっぱり天才で変人だけれど、それよりも人間味がある気がしますしねえ。
悪童サライやベアトリチェとの関係も胸にせまるものがありました。
というか、展示の仕方がスゴイですね……!
雨の降る中、外にはみ出している九十分待ちの長蛇の列。
▽
資料を眺めながら、資料館の中を延々と続く列に並ぶ。
▽
足が痛くなってきた頃に特別なお部屋にようやく到着。
▽
一列に並んで、二、三人ずつ順番に白虎と対面。
▽
十数秒後に係員のお姉さんがさっくりと次を促す。
えええ、そんな、一目千両ー!?
友達と一緒に行ったのですが、細かい議論の余地もありませんでした。。
しかしまあ、あれだけの数のお客さんをさばくにはしょうがないかもしれません。
ダ・ヴィンチ・コードミステリーSPとかいうものを見ています。
……こういうあからさまな便乗番組って嫌いなんですけどねえ……(何で見るんだ)
マリア説は京佐としても好きですし、ダ・ヴィンチ・コードも結構楽しんで読んだのですが、こういう風に「これが真実だ」みたいにやられるのって微妙です。
キリスト教徒の人たちにしてみれば不愉快甚だしいんでしょうしねえ。
世界ふしぎ発見とか、奇跡体験アンビリーバボーとか、あの辺の番組にも見え隠れする押し付けがましさみたいなものがある気がします。
嫌だ嫌だ。
ところで個人的にはモナ・リザをモチーフにした作品なら、カニグズバーグの「ジョコンダ夫人の肖像」の方が印象が深いです。
ダ・ヴィンチ・コードのダ・ヴィンチはどこまでも天才で仕掛け人で多くの謎を遺した人なのですが、ジョコンダ夫人の肖像のダ・ヴィンチはやっぱり天才で変人だけれど、それよりも人間味がある気がしますしねえ。
悪童サライやベアトリチェとの関係も胸にせまるものがありました。
巷では成分解析なるものが流行っているようですね。
しかし普通の成分解析の結果を連ねても楽しいのは身内だけ……ということで、逆転の発想です。
http://seibun.nosv.org/maker.php/jm/
日本神話解析作ってみました。
ワードを100個入れると自動で解析を作ってくれるというステキなサイトを発見したのです。
日本神話用語が100個捻り出せる自分って正直どうかと思うんですが。
あんまりマイナーな神様は入れてない……はずですので、皆様是非お楽しみくださいませ。
ちなみに「京佐」で解析するとこんな感じ▽
京佐の53%は八咫烏に守られています
京佐の28%はコトシロヌシに守られています
京佐の9%はイザナギに守られています
京佐の8%はツクヨミに守られています
京佐の2%はアマテラスに守られています
……八咫烏とか事代主とか、(天神に帰順した国祇という意味での)裏切り者イメージが強い気が……
でもまあ八咫烏=アジスキタカヒコネとすれば、オオクニヌシのお子さん率が高いってことですよね!(ポジティブ)
……でもワタシ、上記の等式があんまり好きじゃないのですけど。
アジスキタカヒコネ、フツーに別項目で入れちゃいましたしねえ。
オオクニヌシとオオモノヌシも分けてますし、その辺趣味出すぎです。。
まあこの解析自体が趣味なので、意地でもヤマトタケルは入れてません。
八咫烏もちょっと悩んだんですけどね。
そんなに好きじゃないから(酷)
因幡の白兎は迷うことなく入れたんですけどねえ。
さて、本名だとこんな感じです▽
○○の77%は豊葦原に守られています
○○の21%はアメノミナカヌシに守られています
○○の2%はイザナミに守られています
豊葦原率が八割に届きそうじゃないですかー!(ガビーン)
既にカミサマじゃないっていうかカミサマの集合体っていうか……
うん……いいんです、国祇ダイスキ!
しかし現在、「オオクニヌシ」が対象から漏れているという重大な事実が発覚(涙)
作り直そうかなあ……
しかし普通の成分解析の結果を連ねても楽しいのは身内だけ……ということで、逆転の発想です。
http://seibun.nosv.org/maker.php/jm/
日本神話解析作ってみました。
ワードを100個入れると自動で解析を作ってくれるというステキなサイトを発見したのです。
日本神話用語が100個捻り出せる自分って正直どうかと思うんですが。
あんまりマイナーな神様は入れてない……はずですので、皆様是非お楽しみくださいませ。
ちなみに「京佐」で解析するとこんな感じ▽
京佐の53%は八咫烏に守られています
京佐の28%はコトシロヌシに守られています
京佐の9%はイザナギに守られています
京佐の8%はツクヨミに守られています
京佐の2%はアマテラスに守られています
……八咫烏とか事代主とか、(天神に帰順した国祇という意味での)裏切り者イメージが強い気が……
でもまあ八咫烏=アジスキタカヒコネとすれば、オオクニヌシのお子さん率が高いってことですよね!(ポジティブ)
……でもワタシ、上記の等式があんまり好きじゃないのですけど。
アジスキタカヒコネ、フツーに別項目で入れちゃいましたしねえ。
オオクニヌシとオオモノヌシも分けてますし、その辺趣味出すぎです。。
まあこの解析自体が趣味なので、意地でもヤマトタケルは入れてません。
八咫烏もちょっと悩んだんですけどね。
そんなに好きじゃないから(酷)
因幡の白兎は迷うことなく入れたんですけどねえ。
さて、本名だとこんな感じです▽
○○の77%は豊葦原に守られています
○○の21%はアメノミナカヌシに守られています
○○の2%はイザナミに守られています
豊葦原率が八割に届きそうじゃないですかー!(ガビーン)
既にカミサマじゃないっていうかカミサマの集合体っていうか……
うん……いいんです、国祇ダイスキ!
しかし現在、「オオクニヌシ」が対象から漏れているという重大な事実が発覚(涙)
作り直そうかなあ……
ハニワなどに見たところ、角髪(美豆良)には大きく二種類があるようです。
耳の辺りで小さくまとめた動きやすさ重視の「あげみずら」と、肩まで垂らした高貴な香り漂う「さげみずら」です。
せっかくなので分かりやすく図示してみました。
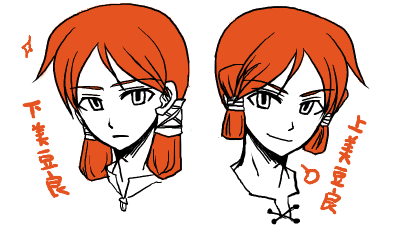
ワカタカブラザーズです。(その言い方は相撲っぽいし止めたほうが)
しかし神代異聞で「角髪」と描写しているのはイタ兄さんと高姫さんくらいでしょうかねえ。
最もポピュラーな古代の髪型のはずなんですけど……
京佐もほんとは下美豆良やってみたかったんですが、長さと根気と高貴さが足りませんでした。
耳の辺りで小さくまとめた動きやすさ重視の「あげみずら」と、肩まで垂らした高貴な香り漂う「さげみずら」です。
せっかくなので分かりやすく図示してみました。
ワカタカブラザーズです。(その言い方は相撲っぽいし止めたほうが)
しかし神代異聞で「角髪」と描写しているのはイタ兄さんと高姫さんくらいでしょうかねえ。
最もポピュラーな古代の髪型のはずなんですけど……
京佐もほんとは下美豆良やってみたかったんですが、長さと根気と高貴さが足りませんでした。
本日の民俗宗教についての授業でのお話。
『西日本の各地において、「虫送り」の儀礼の中で送られるものとして祀られる藁製の人形をしばしば「サネモリサマ」と呼ぶ。
これは平氏の武将として戦った斎藤実盛が稲につまづいたところを討ち取られ、その恨みから害虫に変わったという伝承があるためである。
しかし本当のところは、サイトウサネモリという「サ=穀霊」の音を冠する名前であるために、そのように言われているようである』
とのことでした。
成る程、そういう考え方をするのか、と思ったのも束の間、師曰く。
『広島ではこの藁人形を尼子の霊だとすることもある』
……って、いくら敗者だからって尼子氏を害虫扱いですか!?
地元の方なのでちょっぴり悔しい。むしろ酷い。
最早サの字なんて一文字も入ってませんよ!
と思ってちょっと調べましたら、以下のような文章を発見。
【虫送り】
かつてウンカやニカメイチュウなど稲にとりつく害虫を村から追い出すための「虫送り」の行事がありました。関西ではサネモリ(実盛=稲の虫)送りともいい、いまはかなりすたれているが、それでも観光化して保存されていたり、最近は復活させるところもあります。
虫送りは村中で松明をともし、藁で作ったサネモリ人形を先頭に(実物の害虫を芋の葉や藁づとに入れたりする地方もある)、鐘や太鼓を鳴らし囃しながら田んぼの中のあぜ道を練り歩き、村はずれまで送ります。送る場所は一定していて、いまでも鐘送り場、虫追り塚、虫の山、ウンカの森、虫送り峠などの地名が村々の境に多くあり、青森県五戸町の虫追塚はじめ、高知県南国市の虫塚など大字小字としても各地に残っています(柳田国男「神送りと人形」ほか)。
行事の呼び方も地方により虫祭り(岩手県遠野)、虫落とし(九州)その他ウンカ送り、アマコ追い、テンノコムシなどさまざまで、行事の日も六月から七月にかけていろいろです。練り歩くときの囃し言葉も「ウンカの神送れ」(長野県)とか「なに虫送ればごじりむし送るわ」(新潟県)、「実盛さんはゴショライ、稲の虫はおともせ」(兵庫県)などなど。
稲の虫を実盛というのは、「イナゴは戦死の強者の怨恨の化するところ」という古い中国の思想があり、日本でも非業の死を遂げた霊が浮遊霊となり害虫化したとする考えがあって、平安末期、加賀篠原の戦いで非業の死を遂げた斎藤別当実盛の霊が害虫になったとの故事によっています。
戦死の強者……うん、強者と認識されていただけ……(涙を飲む)
『西日本の各地において、「虫送り」の儀礼の中で送られるものとして祀られる藁製の人形をしばしば「サネモリサマ」と呼ぶ。
これは平氏の武将として戦った斎藤実盛が稲につまづいたところを討ち取られ、その恨みから害虫に変わったという伝承があるためである。
しかし本当のところは、サイトウサネモリという「サ=穀霊」の音を冠する名前であるために、そのように言われているようである』
とのことでした。
成る程、そういう考え方をするのか、と思ったのも束の間、師曰く。
『広島ではこの藁人形を尼子の霊だとすることもある』
……って、いくら敗者だからって尼子氏を害虫扱いですか!?
地元の方なのでちょっぴり悔しい。むしろ酷い。
最早サの字なんて一文字も入ってませんよ!
と思ってちょっと調べましたら、以下のような文章を発見。
【虫送り】
かつてウンカやニカメイチュウなど稲にとりつく害虫を村から追い出すための「虫送り」の行事がありました。関西ではサネモリ(実盛=稲の虫)送りともいい、いまはかなりすたれているが、それでも観光化して保存されていたり、最近は復活させるところもあります。
虫送りは村中で松明をともし、藁で作ったサネモリ人形を先頭に(実物の害虫を芋の葉や藁づとに入れたりする地方もある)、鐘や太鼓を鳴らし囃しながら田んぼの中のあぜ道を練り歩き、村はずれまで送ります。送る場所は一定していて、いまでも鐘送り場、虫追り塚、虫の山、ウンカの森、虫送り峠などの地名が村々の境に多くあり、青森県五戸町の虫追塚はじめ、高知県南国市の虫塚など大字小字としても各地に残っています(柳田国男「神送りと人形」ほか)。
行事の呼び方も地方により虫祭り(岩手県遠野)、虫落とし(九州)その他ウンカ送り、アマコ追い、テンノコムシなどさまざまで、行事の日も六月から七月にかけていろいろです。練り歩くときの囃し言葉も「ウンカの神送れ」(長野県)とか「なに虫送ればごじりむし送るわ」(新潟県)、「実盛さんはゴショライ、稲の虫はおともせ」(兵庫県)などなど。
稲の虫を実盛というのは、「イナゴは戦死の強者の怨恨の化するところ」という古い中国の思想があり、日本でも非業の死を遂げた霊が浮遊霊となり害虫化したとする考えがあって、平安末期、加賀篠原の戦いで非業の死を遂げた斎藤別当実盛の霊が害虫になったとの故事によっています。
戦死の強者……うん、強者と認識されていただけ……(涙を飲む)
